【vol.2】「目指すのは人とAIの共進化」リクルートAI研究所所長が人工知能領域への取り組みを明かす
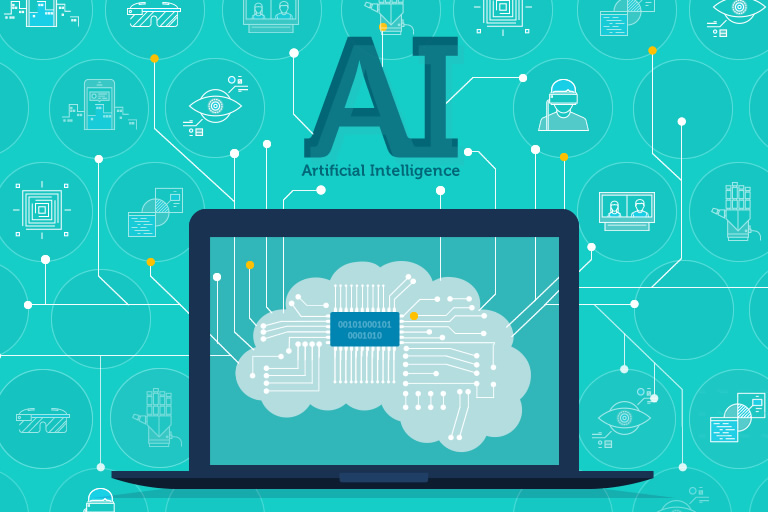
文:モリジュンヤ イラスト:小山 敬介(A.C.O.Inc.)
リクルートは、2015年4月に人工知能研究所として新しく「Recruit Institute of Technology」を立ち上げた。
AI分野の世界的権威であるTom M. Mitchell氏(米カーネギーメロン大学教授)、Oren Etzioni氏(Allen Institute for Artificial Intelligence CEO/元・米ワシントン大学教授)、David M. Blei氏(米コロンビア大学教授)、Alex 'Sandy' Pentland氏(米マサチューセッツ工科大学教授)、Christopher D. Manning氏(米スタンフォード大学教授)らをアドバイザーに迎え、リクルートグループ各社と連携したグローバル規模のAI研究を進めている。
同研究所を率いる石山洸に、リクルートの人工知能領域に関する取り組みと、今後の展望について話を聞いた。

若き所長・石山洸が人工知能に出会った経緯とは?
32歳という若さにして、IT専門の執行役員「IT-EXE」や、リクルート内の実証・研究機関であるメディアテクノロジーラボ(MTL)所長を務めるなど、リクルートの新規事業を担ってきた石山。まずは、石山が人工知能に関わることになったきっかけから紹介していこう。
石山洸(以下、石山) 「大学2年の時に9.11が起き、アメリカの今を自分の目で確かめたくなったんです。ただ、当時の私にはアメリカに行くお金がなかった。そんな時に見つけたのが、とあるプログラミングコンテスト。突破すればアメリカに無料で行けるということで、それまで全く経験のなかったプログラミングの勉強を始めました」
実は、大学時代はコンピュータとは縁遠い文系学生だったという石山。しかも、勉強を始めた時点でコンテストの予選までわずかに2〜3週間と、無謀とも言える挑戦であった。
石山 「当時の自分のレベルは、「マイコンピュータ」をダブルクリックするのが精一杯。それでもなんとか人工知能プログラミングを覚え、入賞することができました。本選が行われたのは、ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学。そこで出会った日本の大学の教授に『君は理転するべきだ』と言われ、理系の大学院に進学し、人工知能の研究に取り組み始めました」
研究室の枠を超え、実社会に役立つ人工知能技術を追求
大学院での彼の研究は「社会に役立つ人工知能」に関するものだった。
石山 「大学院では経済学や社会学、教育など、サイエンス要素が少ない分野に人工知能技術を活用していくための研究を行っていました。修士の時は研究室にこもって2年間で論文を18本も書くような学生でしたが、社会に役立つ人工知能技術を追求していくためには、実際に世の中に導入していくことにも取り組みたかったので、卒業後はリクルートに入社しました」
在学中に助手のポジションをオファーされるなど研究者としての将来を約束されながらも、社会との接点を求めてリクルートに入社した石山。様々な経験を経て、人工知能研究所「Recruit Institute of Technology」のHead of Instituteを務めることになる。
石山 「リクルートでは現在、世界的な人工知能研究者とコラボレーションし、研究を進めています。研究者の方も、ただ大学で研究を行っている方を選定したのではなく、自身で起業をするなど、実社会に人工知能技術を導入した実績のある方々をアドバイザーとして選出している点が大きな特徴だと思います。あくまで、実社会にとって有益な人工知能の研究をしていくのが僕らの研究所の方針なので」
人工知能と社会の関係は、レーズンパンのようなものだ
「人工知能と社会の関係は、レーズンとパンの関係のようである」とは、同研究所のアドバイザーの一人、Oren Etzioni氏の言葉だ。
石山 「"人工知能"と"社会"をレーズンとパンに見立ててその関係性を語るOrenの話が面白いんです。彼曰く、『レーズンとパンは、どちらもそれぞれ食べられるけれど、合わせてレーズンパンにすることで、さらに美味しく食べられる。人工知能と社会も、両者の良いところを融合させて、よりよい社会の構築を目指していくことが大事』だそうです。これは私たちの研究所のミッションとしても、最も重要なことだと考えています」
Oren Etzioni氏は、ワシントン大学の教授を務めていた当時、自身で立ち上げたAIスタートアップをMicrosoftやeBayなどに、計7回もバイアウトした経験を持つ人物だ。自作の論文がどれだけ引用されたかを示す「h-index」という指標でも高い数字を誇り、研究者としても一流でありながら、ビジネスにおいても活躍している。
現在は、Microsoftの共同創業者Paul Allen氏が立ち上げた人工知能研究所「Allen Institute for Artificial Intelligence」の責任者を務めている彼だが、なぜ、研究とビジネスの境界を飛び越える働き方をしているかといえば、「レーズンパンを作りたかった」からだ。
同研究所も、社会と人工知能の良い関係を追求しながら、グローバルスケールでどれだけ早く進められるかに取り組んでいる。ちなみに、石山によれば「Orenはレーズンパンを世界で一番美味しいパンだと思っている 」とのこと。
「レーズンパン型」と「おにぎり型」の研究
「レーズンパン型」の研究と、「おにぎり型」の研究が存在していると石山は語る。「レーズンパン型」はレーズンがパンの中に偏在している状態。これはビジネスとテクノロジーが、社会の中で密接に融合している状態とも言える。一方で、おにぎり型では具が一箇所に固まってしまっていて、社会に馴染みきっていない状態だと言える。
石山 「真ん中に具があって、周囲はお米に囲われている。つまり、外からは何の具が入っているかわからないし、技術が研究所の中だけに閉じていて、社会との接点がほとんどないような状態のことを『おにぎり型』の研究と呼んでいます。中央研究所などに多い形態ですね。基礎研究の独立性等の観点から必要なことではあるのですが、インターネットの世界では中央研究所の考え方が、徐々にレーズンパン型へと変わってきています」
石山たちは研究所内で「中央研究所が溶けだしている」と表現しているという。社会との接点をもたず、研究だけをひたすら追求していた状態から、少しずつ社会との接点を持ち、実用に向けた動きをとるところも増えてきた。たとえば、Googleのリサーチ内容を紹介している「Research at Google」のページでは、Googleの研究手法自体が現場と密接に関わっていることが示唆されている。
石山 「Googleの研究は、現場ドリブン、買収先ドリブン、リサーチ部門ドリブンのものなど、いろいろなパターンがありますが、現場と研究が一体となりながら、柔軟に役割を組み替えて研究開発している点が特徴です。Hadoopの一部のアルゴリズムなんて、現場のエンジニアが考えたそうなんです。そうなると、中央研究所はなんのために存在するのか。海外の研究の主流はレーズンパン型になってきていますが、日本はまだおにぎり型が多い印象です。そもそも、日本では大学の先生が起業する例もまだそれほど多くはなく、アカデミックとビジネスの融合が進んでいません。現場も応用研究も、それぞれの独立性が高すぎるがゆえに、現場の技術も研究開発もスピードが上がらないということが起こっています」
こうした研究と現場の融合は、人工知能技術においては特に重要なことだと石山は語る。
石山 「人工知能はインプットされるデータによって進化していきます。高速でプロダクトアウトしながらデータを集め、それをベースにアルゴリズム自体を改善していくことが必要です。そうすると、どうしても現場との一体感が重要になり、ガバナンスを含めてマネジメントしていくことが研究所に求められます」

HR領域におけるグランドデザインを共に描く
社会と関わりながら人工知能の研究を行っている同研究所では、多様な研究者たちがアドバイザーとして関わっている。彼らは一体どのように研究に携わっているのだろうか。
石山 「米カーネギーメロン大学教授のTom M. Mitchell氏とは、ビジネスと研究をどう融合させるか、どういうリサーチテーマを作るかなど、かなり上位から一緒に戦略設計をしています。彼は、『Machine Learning』という書籍を書いた人物で、同大学でコンピュータサイエンスとマシンラーニングという2つの学部のトップを務めているだけでなく、マシンラーニングの学部を作った人物でもあります。また、立ち上げたスタートアップをMonsterという北米のHR系の大手企業にバイアウトした経験もあり、HRを含めたリクルートのビジネスモデルにも精通している人物。リクルートがどんな研究をしていくべきかといったグランドデザインについてもアドバイスをもらっています」
ビジネスとの連携が重要だと考えている石山は、リクルートの主な事業領域である人材ビジネスにおける人工知能の活用に関しても、Tom M. Mitchell氏からアドバイスをもらっているという。
続いて、米コロンビア大学教授のDavid M. Blei氏について。
石山 「David M. Blei氏は、自然言語解析(正確な文法に則った言語ではなく、我々が日常使う口語や音声などの言語を正しくコンピューターに認識させるための解析方法)を行っている人が100%使用していると言われるLDA(Latent Dirichlet Allocation)というモデルの生みの親です。リクルートにとってなぜ自然言語が重要かというと、例えば人材領域で言えばレジュメなどのジョブディスクリプションはすべて自然言語で書かれています。ソーシャルメディアにも自然言語は数多く含まれており、自然言語を解析していくことで、これまでわからなかったことがわかるようになる。そのため、自然言語解析とマシンラーニングの領域は重要なんです。彼からは、データを分析していくにあたって、いろいろアドバイスをもらっています」
前述のTom M. Mitchell氏と進めているプロジェクトで発生した自然言語解析における課題を、David M. Blei氏にアドバイスをもらいながら解決していっているというような状況だという。
石山 「Davidは一度打ち合わせをすると、10本くらい論文を送ってきて、『次回までに読んでおくように』と言ってくるんです。僕らはかなりのスピード感を持ってプロジェクトを進めているので、フィードバックを受けてアルゴリズムを改善し、次回のミーティングまでには相当プロダクトを進めた状態になっている。彼らとしても、日本の大企業とは思えないスピード感で僕らがプロジェクトを進めているので驚いてくれ、いい関係を築けています」
また、自然言語処理の大家として知られる米スタンフォード大学教授のChristopher D. Manning氏も、9月からビジティングリサーチに就任することが決まっているという。
IoTやオフィスセンサーによるビッグデータ解析も視野に
米マサチューセッツ工科大学教授のAlex 'Sandy' Pentland氏は、人間行動とセンサー、プライバシー研究を掛け合わせたビッグデータ研究に取り組んでいる人物。
石山 「リクルートはマッチングビジネスがメインのビジネスモデルですが、通常Web上で取得出来るマッチング前の行動データだけではなく、マッチング後のビジネスデータも取得するようにしています。例えば転職者・転職者を受け入れた企業両方に転職してから6ヶ月後にヒアリングをして、満足しているかどうかを調査すると、本当に幸福かどうかがわかるようになっています。Web上でのコンバージョンデータからは、ユーザの気持ちを類推することしか出来ませんが、実際に後追いをして、本当に有益なマッチングができたか、というデータまでをそろえて考えられる。この点についてAlexは『Googleも持っていないデータだよ、素晴らしいね』と言っています」
Alex 'Sandy' Pentland氏とは、特にIoTやセンサーなどの領域で様々な可能性を模索しているという。
石山 「たとえば、オフィスセンサーやウェアラブルデバイスなど、何らかの端末を用いてセンシングを行い、データを取得できるようになると、そのデータを用いてより良いマッチングが可能になります。 Alexは人×センサーの領域におけるビッグデータ解析で有名な人なので、そういった領域も視野に入れながら産学連携を行っています」
ビジネスとの接続が進み、現場と研究が一体となりハイスピードで進んでいくのが海外の潮流だ。しかし、研究レベルは高いが接続がうまくいっていない、もしくは現場との接続はうまくいっているが研究レベルがそこまで高くないなど、バランスがとれているところは少ない。リクルートは、研究レベルの高さと現場との接続の両方を進めていくことを目指している、と石山は語る。
人間とAIの共進化を目指す
人工知能に関してはポジティブな話ばかりではなく、ネガティブな意見が飛び交うことも珍しくない。長く人工知能研究に携わってきた石山は、人工知能の未来についてどのように捉えているのだろうか。
石山は、「コンピュータの歴史をもう一度辿ることでこれからの歴史が見えてくる」と語る。
かつてコンピュータといえば、スーパーコンピュータのようなとても巨大で、マウスも、インターネットも、GUIもないものを指し、物理計算の処理等に用いられる程度だった。だが、やがて人類はパーソナルコンピュータを生み出し、生活やビジネスなどあらゆる場面で利用されるようになった。現在では、その市場はスーパーコンピュータよりも大きくなり、企業はPCなしではビジネスは成り立たないようになっている。こうした流れが人工知能においても起こる、と石山は考えているのだ。
石山 「研究題材におけるAIから、パーソナルなAIへとダウンサイジングしていくと思います。人間と人工知能を組み合わせることで、高い付加価値を生み出すような方向へと向かっていく。リクルートのAI研究所は、 人間とAIの共進化をテーマにしています」
人工知能が目指す未来とは、自動的にすべてが決められてしまい、人間の選択肢を狭めてしまうような未来ではなく、まだ人間が気づいていないような選択肢を浮かび上がらせるような、機会の最大化を図る未来を目指すことである。と、石山は定めている。
石山 「リクルートホールディングスが果たす役割として挙げている『まだ、ここにない、出会い』......英語で言うと『Opportunities for Life』 を最大化していくために、どのように人工知能を活用していくのか。アドバイザーの研究者も交えて、日々議論しています」
そして最後に「人工知能とは、そんな難しいものではない」と石山は付け加えた。
石山 「簡単に言ってしまえば、明日の天気を当てるためのロジックを考えるようなものなんです。予測をするためには、判断材料集めとロジックの精度を高めることが必要になります。最近では、精度を高めるためのテクノロジーが進化し、判断のためのデータが取得しやすくなった。そのため予測が当たりやすくなってきました。予測が当たりやすくなってきたことで、ビジネスとして成立しやすくなり、ビジネスモデルが確立されてきました。さらに、ビジネスモデルが確立されたことで、データを取得するための手法の開発に投資家が投資をするようにもなってきたので、注目度も上がってきています」
同研究所は、グローバル規模でオープンイノベーションを実現するべく、すでに米国やイスラエルのAI関連企業との協業も開始している。彼らが実現する「人間とAIの共進化」がより良い未来を切り開いていく。
プロフィール/敬称略
- 石山 洸(いしやま こう)
- Recruit Institute of Technology 推進室 室長
-
2006年、東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻修士課程修了し、リクルート入社。インターネットマーケティング室などを経て、全社横断組織で数々のWebサービスの強化を担い、新規事業提案制度での提案を契機に新会社を設立。事業を3年で成長フェーズにのせバイアウトした経験を経て、2014年、リクルートホールディングスのメディアテクノロジーラボ所長に就任。2015年より現職。





